「万引き」が増えています
万引きは、はじめは軽い気持ちでも、これをくり返しているうちに罪の意識が薄れ、さらに大きな罪をおかすようになります。

万引きとは、スーパーマーケットや文房具店、おかし屋さんなどで、お金を払わないで、品物をこっそり持って来てしまうことです。

万引きは、一度やって見つからないと、またやりたくなって、その次もまた、その次もとくり返しやってしまいます。
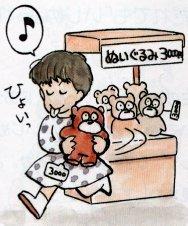
見つからなかった万引きを友だちにじまんして話しているうちに、これが遊びのように広がり、悪いことをしているという気持ちが心からだんだんに消えてしまいます。

ふざけ半分で万引きしている人もだんだんにホンモノの悪い人になってしまいます。
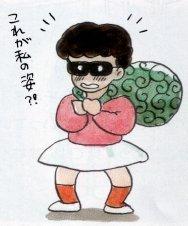
万引きは、ドロボーです。見つかってから品物をかえしても、お金を払っても、警察に補導されます。
保護者のみなさんへ
反省がなければより重い犯罪へ
子どもの万引きは、そのほとんどがスリルや刺激を求めての行為です。主な理由は「興味本位で」「ゲーム感覚で」「仲間がするから」などです。しかも、万引きで補導された少年の多くは、「悪いことをした」という意識が薄いと指摘されています。
万引で捕まったのは「運が悪かったから」としか考えられない子どもは、次はもっと重大な犯罪に手を染める可能性があります。子どもの態度や言葉から罪悪感の乏しさを感じ取った場合、親ははっきりとした倫理観を示して子どもに注意を与えることが大切です。万引きや自転車盗などの行為は「犯罪」であることを、子どもにしっかりと理解させなければなりません。
親の態度が子どもの倫理意識を育てる
もし、子どもが万引きをしてしまった場合、例えば「世間体がよくない」などという理由で子どもをしかるのは逆効果です。これでは、「盗みはいけない」というメッセージは伝わりません。
子どもの万引きで呼び出された親が、お店の人に「お金を払えばいいんでしょう」と言ったというケースもあるそうです。子どもをかばおうとする気持ちの表れかもしれませんが、こうした親の態度を目にした子どもが反省することはありません。やはりきちんと頭を下げる親の姿を見せてこそ、子どもは「悪いことをした」という思いを胸に刻むものです。
万引き・盗みのサインの例

見慣れない物、高価な物を持っている。
親のサイフからこっそりお金を持ち出していた。
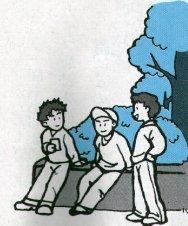
グループで遊びに出かけ、街でぶらぶらしている。
親の注意を引きたくて
「親の注意を引きたくて」という理由で万引きをするケースもあります。この場合、子どもは万引きを「悪いこと」と認識した上で、自分のさびしさを訴える手段として非行に及んでいるのです。
このように、子どもが「自分への親の愛情や関心が薄い」と感じていると、万引きに限らず、さまざまな問題行動につながるおそれがあります。子どもの話をじっくりと聞くように努めてください。
このページは、日本広報協会「子どもの心に向き合う心」、けいさつ「もう一度考えよう」を利用しました。
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会事務局学校教育部少年愛護センター
〒664-0898伊丹市千僧1-1総合教育センター3階
電話番号072-780-3540 ファクス072-770-9471
- このページの感想をお聞かせください
-


更新日:2021年03月31日