2025年10月~12月
目次
【12月25日】クリスマス・イブ、伊丹の街の様子は…
【12月23日】親子で学ぶ、日本の武道文化――修武館で「なぎなた体験」
【11月13日】俳句を通して"ことば"と出会う 坪内稔典流 俳句講座に潜入!
【10月31日】ハロウィンでつながるまちと人 ― いたみハロウィンパーク&ツアーに参加してみた!
【10月24日】第45回 いたみ花火ダイジェストムービーを公開!
【10月10日】災害現場などで救助活動を支える新たな仲間『新 救助工作車』が登場!
12月
【12月25日】クリスマス・イブ、伊丹の街の様子は…
郷町〇店:江戸町家で楽しむクリスマスのホットビールとスイーツ
市立伊丹ミュージアム内の旧石橋家住宅でたびたび開催されている「郷町〇店」。
12月24日・25日はホットビールとスイーツのセットが楽しめるということで、お邪魔してきました。
ビールの本場であるベルギーやドイツでは、寒い時期などに温かいビールを飲む習慣があり、クリスマスマーケットでもおなじみだそう。

チェリー&ベリー味のホットビールとチョコ味のチーズケーキ

お気に入りのビールを見つけたらお持ち帰りも可能です
関連リンク
市立伊丹ミュージアム:江戸町家で楽しむクリスマスのホットビールとスイーツ
クリスマスとまち灯り
駅前の酒蔵通りでは、「クリスマスとまち灯り」の行灯が。
あいにくの空模様だったので行灯の数は少なめでしたが、それぞれの行灯が異なるサンタの絵柄で、1つ1つをよく見てみるのも楽しめました。

お店の軒先に行灯がずらり

いろんなサンタの絵柄が描かれています
【12月23日】親子で学ぶ、日本の武道文化――修武館で「なぎなた体験」
12月13日(土曜)、なぎなたの聖地として知られる伊丹市・修武館※で、小学生を対象とした親子参加型の「なぎなた体験」が開催され、約20組の親子が参加されました。
**********************************
※修武館とは・・・「修武館」は天明6年(1786年)創設の歴史ある道場です。


当日は、市立伊丹高校なぎなた部の生徒の皆さんの協力のもと、参加者は袴に着替え、少し緊張しながらも期待に胸をふくらませて開始を待っていました。全員がそろった後、修武館担当者の神殿に「礼」という合図とともに体験会がスタート。開会あいさつに続き、修武館の歴史や、なぎなたについてのお話しが行われました。


準備運動で体をほぐした後は、市立伊丹高校なぎなた部の生徒によるなぎなたの紹介と実演へ。参加者は真剣な表情で説明に耳を傾け、迫力ある演武に見入っていました。
特にリズムなぎなたの実演では、「やった!」「すごい!」などといった声が上がり、会場は一気に和やかな雰囲気に包まれました。


続いては、なぎなたの防具の説明を受け、いよいよ実技体験スタート!全員になぎなたが配られ、様々な「構え」に挑戦しました。難しい動きには、講師や高校生が一人ひとりに寄り添い、手取り足取り丁寧に指導。


一通りの構えを覚えた後は、防具を着けた高校生に、面打ちや、すね打ちなど実践的な体験も行われ、初めてとは思えないほど生き生きとした姿が見られました。

体験の締めくくりは、全員でリズムなぎなたを実践!軽快な音楽に合わせ、これまでに学んだ動きを生かしながら、親子で楽しく体を動かしました。


最後は全員で改めて、神殿に「礼」を行い、閉会あいさつで体験会は終了しました。

子どもだけではなく、大人が真剣な表情を見せる場面もたくさんあり、親子で同じ体験を共有する貴重な時間となりました。なぎなたは、武道として伝えられてきたものであり、「礼に始まり礼に終わる」と言われるように、礼儀を大切にしてきた文化です。
なぎなたの聖地・伊丹で親子で歴史と文化に触れる実体験は、参加者にとって心に残る思い出になったのではないでしょうか。
終了後には写真撮影会も行われ、武道の精神にふれた余韻を胸に、疲れを感じさせない笑顔で、参加者は修武館を後にしました。
ぜひ、このレポートを読んで興味を持ったみなさま!聖地と呼ばれるここ"伊丹"でなぎなたに触れてみてはいかがでしょうか?
お問い合わせ
「修武館」公式サイト ▼ 修武館
11月
【11月13日】俳句を通して"ことば"と出会う 坪内稔典流 俳句講座に潜入!
10月28日、令和7年度かきもり文化カレッジ「かきもり俳句コース」に参加しました。
このカレッジは全9回にわたり、3人の先生が順に講義を担当します。今回は、伊丹大使で、柿衞文庫理事長の坪内稔典先生の回に参加。
いつもは「市立伊丹ミュージアムの講座室」で行われますが、この日は特別に図書館「ことば蔵」での開催。坪内先生の講座は全3回構成で、今回はその最終回。今回の講座の内容は・・・
「席題」と「兼題」の2部構成で行われ、まず前半は、その場でお題が発表される「席題」からスタートしました。


■ 前半:「席題」― 図書館をテーマに一句
この日の席題は「図書館」。
受講者の皆さんは席に着きホワイトボードに書かれている「席題」を知り、講座が始まるまでに1句を考え、先生へ提出します。どんな発表になるのか、少し緊張とわくわくが入り混じった空気の中、講座が始まりました。坪内先生はこう話します。
「席題のように突然お題を与えられると、思いがけない力や発想力が出たり、普段とは違う句が生まれたりする。それも俳句の面白さなんです。」
発表では、先生と受講生代表の方が前に立ち、提出された句を一つずつ読み上げます。自分が良いと思う句にそれぞれ挙手し、多数決で進む"俳句トーナメント"のような形式。句が紹介されるたびに坪内先生のコメントが入り、さらに挙手をした人に坪内先生が会場をマイクを持ちながら歩き「なぜこの句を選んだのか」を語り合うなど、活発なやりとりが行われました。
筆者のイメージでは、俳句というと静かに詠んで講評を受けるイメージですが、この講座はまるでディスカッションのよう。笑い声や感嘆の声があふれるアットホームな空気に、会場全体が温かく包まれていました。
「図書館」という題材から生まれた多彩な句の数々に、私自身も共感したり驚いたり、ことばの奥深さを改めて感じました。


■ 後半:「兼題」― 晩秋をめぐる言葉たち
後半は「兼題」と呼ばれる課題句の時間。
今回のテーマは「晩秋」「秋の暮」「秋深し」などを使い、事前に一句を考えてくる、いわば"宿題"のようなものです。
この日は22名の受講者が参加。それぞれの秋を詠んだ22句が一覧になった紙を見ながら進行。それぞれの句を読み上げ、良いと思った句に挙手で投票します。票を多く集めた句については、良かった理由を発表し、さらに今回はあえて「なぜ手を挙げなかったのか」も尋ねるというユニークな進め方でした。
選んだ理由も選ばなかった理由も、俳句を読み解く大切な視点として坪内先生が丁寧に拾い上げ、全員で意見を交わします。
最後にその句を詠んだ方の名前を聞き、句に込めた思いや情景を語るなどの時間が流れました。俳句を通してことばを味わい、互いの感性を尊重し合う、温かな時間が流れていました。


■ 坪内先生に聞く、俳句とことばの魅力
講座の終わりに、坪内稔典先生にお話を伺いました。
――俳句を教えるときに大切にしていることは?
「僕の場合は"みんなで話し合うこと"を大事にしています。俳句のよさを、みんなでどこをどうしたらもっと良くなるか考える。先生が一方的に話すのではなく、みんなで議論しながら進めると、よりいいものが生まれると思うんです。」
――講座中、いつも笑顔が絶えませんね。
「僕の場合はそうですね。コミュニケーションを大切にしているので、マイクを向けてみんなに話してもらうようにしています。発表するだけでなく、話して参加してもらうことで、場が明るくなるんです。」
――受講者の句を読むときは、どんな視点で見ていますか?
「"いかにも俳句らしい俳句"というのはあまり歓迎しません。意外性があったり、"あっ!"と思わせる句がいいですね。今回もそうした句がたくさん出ていましたよね。」
――初めて俳句に触れる方に伝えたいことは?
「言葉を使うことの楽しさを見つけてほしいです。言葉は伝達の一番大切な道具なのに、"書くのは大変""話すのは苦手"と思っている人が多い。でももっと気軽に言葉を使ってみると面白い。俳句は5・7・5という"仕掛け"があることで、自由に話したり書いたりできるようになる。それを味わってもらいたいですね。」
――最後に、俳句の魅力とは?
「5・7・5という形式を通して、普段とは少し違う言葉づかいをすること。そのことで心身が少し新しくなり、"違和感"が生まれる。その感覚が気分をよくしてくれるんです。」

■ 取材を終えて
坪内稔典先生の講座は、まさに「アットホーム」という言葉がぴったり。
笑い声やうなずきが絶えないあたたかな空間には、坪内先生の人柄と、ことばを大切にする姿勢があふれていました。
俳句には季節を映す"季語"があります。
秋が過ぎ、ぐっと寒くなり、冬の気配が近づくこの頃。
身のまわりの風景や心の動きを、5・7・5のリズムにのせて表現してみてはいかがでしょうか。
使ったことのない言葉を調べてみたり、新しい表現に挑戦したり。
俳句を通して"ことば"の奥深さと楽しさを、あなたも感じてみませんか?
お問い合わせ
市立伊丹ミュージアムでは「かきもり文化カレッジ」として、俳諧・俳句にかかわる実作講座や柿衞文庫の収蔵品に親しむ講座を開講しています!
※各講座の詳細や最新情報は、市立伊丹ミュージアムのサイト内の「講座」のページをご確認下さい。
10月
【10月31日】ハロウィンでつながるまちと人 ― いたみハロウィンパーク&ツアーに参加してみた!
10月25日(土曜)に行われた「いたみハロウィンパーク&ツアー」。
今年で5回目を迎えた本イベントは、三軒寺前広場を拠点に中心市街地の店舗・事業者と連携して実施する参加型ハロウィンイベントです。
仮装した子どもたちが協力店を巡る「ツアー」、そして広場での「パーク」では、マルシェ&ステージが一緒に楽しめます。
【パーク】マルシェ&ステージ
ステージでは、アーティストによるライブパフォーマンスやプロカメラマンによる記念撮影ありの「伊丹ハロウィンコレクション(ファッションショー)」を開催。
他にもワークショップブースやスタンプラリーなど、子どもから大人まで笑顔になれる企画がたくさん。
三軒寺前広場には朝からおいしい香りが広がり、飲食・物販などの個性あふれるお店がたくさん並び、会場内には仮装した愛犬と一緒に来場された方も。



【ツアー】ハロウィンツアー
そんな中、仮装した子どもたちが次々と集まり、各チーム市内協力店を巡る準備でワクワク・そわそわ。
スタート時間になると、「行ってきまーす!」と声をあげ、小さな手を大きく振りながら歩き出します。
お店の前に着くたびに元気いっぱい「トリックオアトリート!」と声をあげ、お菓子をもらって大はしゃぎ。
協力店の皆さんからは「かわいい~!」「また遊びに来てね~」と声をかけてもらい、子どもたちも嬉しそう。


パーク&ツアーは午前・午後で約200人の子どもたちとその保護者が参加。
知らなかったお店を訪れ、お店の方からお菓子をもらう――街の人との交流が少なくなっている今、貴重なイベントだなぁと思いました。
参加者からは「大きくなったらまた来ようね」「こんなお店があったんだ!」といった声も聞こえてきて、ほっこりしたひと時が広がっていました。
市外から参加したご家族からは、「伊丹は毎週たくさんイベントをしていて。このイベントもちょうどいい距離で子どもたちと一緒に回りながら楽しめるのがよくて、今年も参加しました」というお声も。

おわりに
開催を楽しみにする人が年々増え、今では人気イベントとして定着しつつある本イベント。当日は2,000人以上が来場し、この日は伊丹の街中が子どもたちの仮装と笑顔、ご家族の楽しそうな様子や地域の方との温かい交流に溢れた一日となりました。
街を巡りながら感じるワクワクや、ほっこりするやり取りのひとつひとつが、伊丹の魅力を再発見する時間になったように思います。
これからも、地域みんなで楽しめるこのようなイベントが続いていくことを願う、素敵な一日でした。
(補足:今回よりイベント名称が「いたみハロウィンツアー」から「いたみハロウィンパーク&ツアー」へ変更されました。)
【10月24日】第45回 いたみ花火ダイジェストムービーを公開!
10月18日(土曜)に行われました 「第45回いたみ花火大会」
今年のテーマは「花火物語」
雨の中での開催となりましたが、たくさんの方が会場に足を運んでいただきました。
今年は「六つの物語」をイメージした花火が打ち上がり、ひとつひとつの物語が夜空に描かれるたびに、会場から歓声があがっていました。
雨の粒も光に混ざり合いながら咲いた、六つの物語。
動画でどうぞゆっくりご覧ください。
【10月10日】災害現場などで救助活動を支える新たな仲間『新 救助工作車』が登場!
今回は、市役所の隣にある伊丹市消防局 西消防署に今年の2月より運用開始となった
『新救助工作車』の取材を行いました。動画とともにレポートをお楽しみください。
まず『救助工作車』とはなにか知っていますか?
人命救助のエキスパートである救助隊(レスキュー隊)が乗車する車両で、火災・交通救助・水難救助又は一般生活で起こりうる救助に対応可能な『資機材を積載している車』のことなんです。
そんな『救助工作車』に"新"がついた!…と言うことは何が変わったのか!?
1. シャッターの中には最新式の救助資機材を導入!
2. LEDによる高性能照明!


3. 車両キャブ内の空間の拡大による救助活動初動体制の迅速化!
4. リモコンによるクレーン操作が可能!


など、救助活動を支える最新の装備が満載。
それではそんなかっこいい『新救助工作車』の様子を動画でぜひご覧ください。
実際に、近くでみると車体の大きさと装備の多さに圧倒されました。中でも、2.9トンの重さを持ち上げられる全長10メートルもあるクレーンのすごい迫力!
とくに車体の中にある装置は合理的に配置されており、限られたスペースに必要な資機材が効率よく収納されていることに驚きました。
また、今回は特別に運転席に座らせてもらいましたが、車の大きさ以上に、市民の命を守る現場の"重み"が伝わり、最新の装備だけでなく、それを使いこなす隊員のみなさんの高い意識とチームワークこそが、市民の安全・安心を守っているのだな、と改めて感じました。
「新救助工作車」がおもちゃになって登場!
そして、なんとみなさま!前文に紹介しました『救助工作車』がおもちゃになって9月より発売されているのはご存知ですか? その名も「のりものこれくしょん」!(販売元:株式会社エフトイズ・コンフェクトさま)
実物を購入してみたのですが…LED照明や西消防署の消防車体に描かれているデザインなど、とにかく細かい部分までが実物そのもので、なんとクレーンは自分で伸ばすことができるんです!
消防局担当者の方に「数ある救助工作車の中でなぜ伊丹市が選ばれたのか」をお聞きしたところ、「工作車の車体デザインが魅力的だった」とのことです。
伊丹市の西消防署の車体に描かれているデザインは伊丹市を象徴する飛行機をイメージしたイラストとfireの「f」、itamiの「i」が合わさり一つのデザインとなっているんです。
※画像は実際の商品とは多少異なる場合があります。
※記載の情報は予告なく変更になる場合があります。


消防局Instagramを紹介
最後に…すでにご存知の方も多いかもしれませんが、伊丹市消防局ではInstagramを開設中!市民のみなさんの安全を守るために活躍されている消防士のみなさんの日々の訓練風景やバズった体幹トレーニング、そして動画で役立つライフハックなども紹介!ぜひこの機会に登録してみてはいかがでしょうか?

おわりに・・・・
さて、今回のレポートはいかがでしたか?
『新救助工作車』と言う心強い仲間が加わることにより、災害現場などでの救助活動がこれまで以上に迅速で確実なものになることがわかりました。
伊丹市の消防力がさらに高まることで、"安心して暮らせるまち・伊丹"が一層実感できそうです。
消防局の皆さんの日々の努力に、改めて感謝の気持ちがわいた取材になりました。
貴重な体験とご協力、本当にありがとうございました。
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 経営戦略室 広報・シティプロモーション戦略課
〒664-8503 伊丹市千僧1-1(市役所3階)
電話番号 072-784-8010 ファクス 072-784-8107
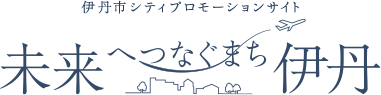
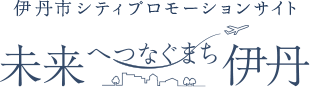
更新日:2025年12月25日